
介護職の賃上げ率は2.52%。今後の予想は?
介護業界は「賃上げが遅れている」「給与水準が低い」と言われてきました。
そこで政府ではさまざまな取り組みを行い、2024年には介護職全体で賃上げがなされました。
しかし他産業と比較すると、賃上げ率はイマイチな結果となりました。
本記事では、介護職の賃上げ状況、賃上げが遅れている理由、賃上げに必要なことをご紹介します。
介護職の賃上げ状況
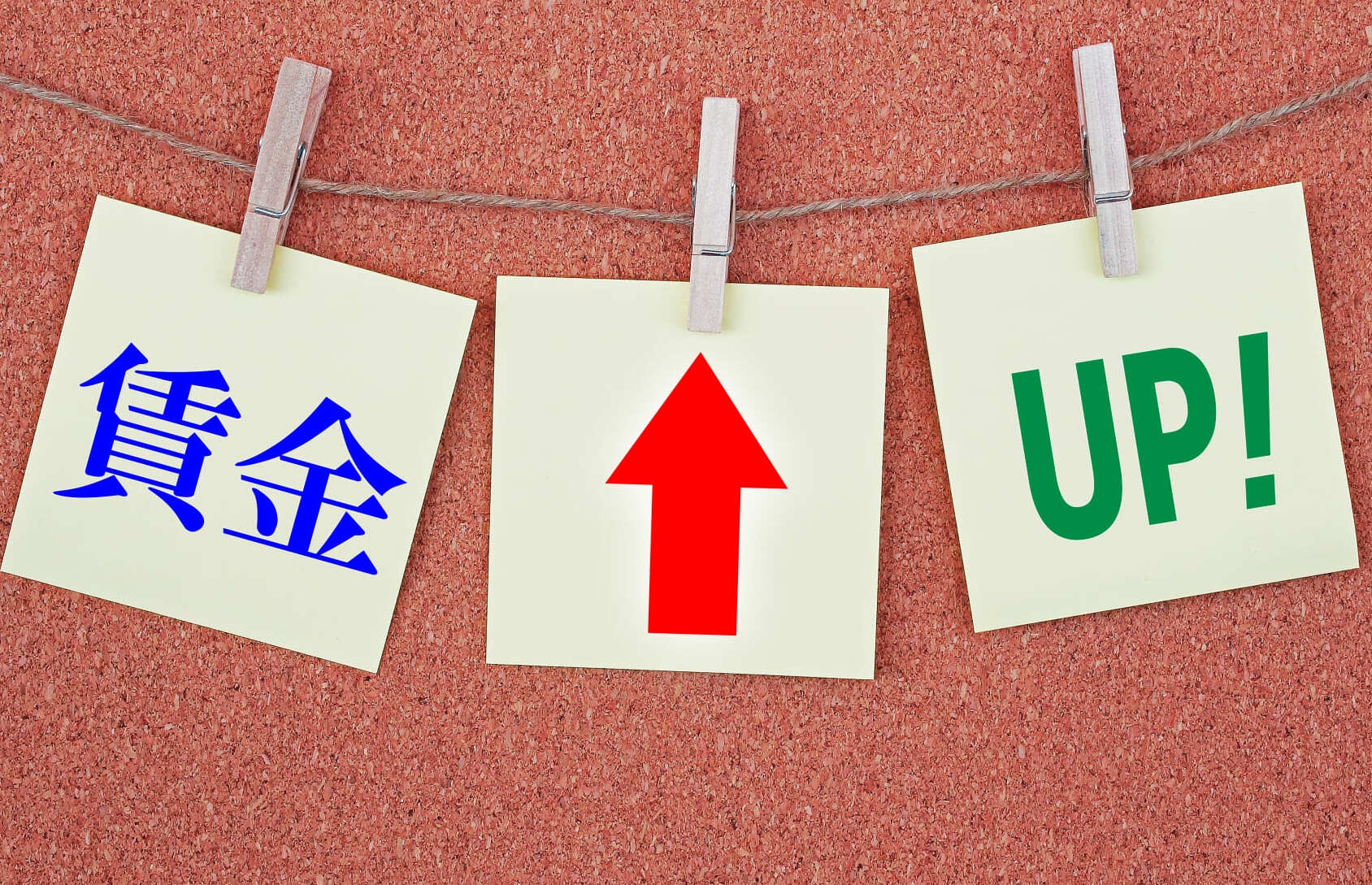
「全国老人保健施設協会」や「全国介護事業者連盟」を含む介護関連の9団体が行った調査によれば、2024年度の正社員として働く介護職の賃上げ額は平均6,098円で、賃上げ率は2.52%であるとされています。
この額は前年度の4,600円から比べると、133%上昇しています。
前年度比で100%以上上昇した背景には、2024年の介護報酬の改定に先駆けて、政府が介護職の賃金改善を行うために支援したことが挙げられます。
高齢化が進む日本では介護職の需要が高まっていますが、賃金水準が低く、人手不足が常態化しており、人材確保・定着のために国を挙げて賃上げを実施したと考えられます。
しかし、前述の調査によれば、今年度の春闘での賃上げ率は5.10%(中小4.45%)とされています。
つまり、介護職は他の業界に比べると賃上げ率が大きく下回っていることがわかります。
介護職の賃上げはある程度進んでいるものの、他産業や他職種との格差は拡大しています。
介護職の人材確保・定着を進めるためには、さらなる賃上げが必要といえるでしょう。
出典:全国老人保健施設協会/「緊急!「介護現場における物価高騰・賃上げ等の状況調査」結果」
介護職の賃上げが遅れている理由
介護職の賃上げが遅れる理由はさまざまあります。
なかでも直近の理由として挙げられるのが、物価高騰です。
前述の調査によれば、特別養護老人ホームでは2020年6月と比べて電気代が55%増加していることをはじめ、ガス代や燃料費などさまざまなコストが増加しています。
こうした背景が介護事業者の経営を圧迫し、賃上げ上昇力の鈍化につながっているようです。
他にも、介護職では以前から以下のような理由で賃上げが遅れやすいとされています。
非正規労働者の割合が多い
介護職は非正規労働者の割合が多く、そのために賃上げが進みにくいといわれています。
介護施設は、未経験者を含めてどんな人でも働きやすい職場です。
そのため、アルバイトやパートなどの非正規雇用の職員が多く働いています。
非正規雇用職員は、正職員と比べると昇給制度が整っておらず、福利厚生も充実していません。
また基本的に正社員よりも賃金が低く、アルバイトやパートの職員は給料がアップしにくくなっています。
そうした非正規労働者の割合が多いことから、介護職全体で賃上げが進みにくいと考えられています。
介護報酬の仕組み
介護職の賃金が上がりにくい理由として、介護報酬の仕組みも挙げられます。
介護職員の給料は、国から支給される介護報酬から支払うことになっています。
介護報酬を増額できれば、介護職の賃金は自然に上昇しやすくなります。
しかし、介護報酬は国から支払われるものであり、増額すれば財源を確保するために増税しなければなりません。
増税すれば税収は上がりますが、国民の負担が増大するため、介護報酬は安易に増額できるわけではないのです。
このような介護報酬の仕組みにより、介護職員の賃金を上げるのは難しいとされています。
介護職の賃上げに必要なこと
介護職の賃上げに必要なこと、それは賃金と介護報酬制度の見直しです。
2024年の介護報酬改定は、2年分の賃上げが含まれていますが、2025年の賃上げは困難だとされているため、来年度に向けて新たな対策をすべきとされています。
また、介護従事者が行える賃金アップの方法としては、資格取得や正職員になることが挙げられます。
正職員になれば非正規雇用のアルバイトやパートよりも賃金ベースがアップします。
資格取得でさらなる賃金アップが期待できることでしょう。
他にも、手当が支給される夜勤を行えば、賃金をアップできます。
今後も賃上げは期待されるもののさらなる対策が必要
2024年の介護職の賃上げ率は2.52%と上昇したことで、介護職の賃金状況は改善されてきております。
しかし、他産業に比べると賃上げ率は低く、物価高騰も相まって、いまだに介護職の給与水準は高いとはいえません。
高齢化社会が進み介護職の需要が高い状況の中、低い給与水準である状況は好ましいとはいえないでしょう。
政府ではさまざまな対策を行っているものの、さらなる対策が求められます。
また、介護職の賃金が低い理由として、アルバイト・パート職員が多いことも挙げられますので、正職員として働く、資格を取得するなどによって自力で給与をアップを目指していく取組みも必要といえます。
しっかりとした賃金の対価をもらいながら、社会的貢献度の高い介護職を続けていくためにも、自分で行える取組みは積極的に検討していきましょう。


